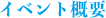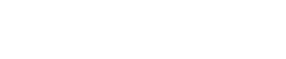企画主旨
「土方巽 1960 しずかな家」は、2014年11月、2016年4月の2度にわたって横浜市西区赤門町にある光明山東福寺およびその周辺で行われたアートイベントである。
ノンフィクション作家・檀原照和が発起人となり、檀原の趣旨に賛同するダンサー、役者、音楽家、舞踊批評家らが出演した。
本企画にその名を残す「土方巽(ひじかた・たつみ)」は前衛芸術の世界に強い影響を与えたダンサーである(1928年生〜1986年没)。土方は1960年に、京急線・黄金町駅から徒歩5分の赤門町で暮らしていた。
土方の盟友に同じく舞踊家の大野一雄がいる。大野の功績を称える冠イベント「大野一雄フェスティバル」が毎年 BankART Studio NYK 主催で行われているが、土方の名を冠したイベントはない。
本イベントは黄金町駅周辺エリアの地域資源として、前衛舞踊表現である「舞踏」の創始者・土方巽に光を当てるものである。
土方巽について
ダンサー、振付家。
1928年秋田県生まれ。18歳の頃江口隆哉門下の教室でノイエタンツ(ドイツ的なモダンダンス)を学ぶ。安藤三子舞踊研究所を経て1961年に「暗黒舞踏派」を名乗る。
1960年代初頭、「舞踏」という新しいジャンルのダンスを創造し、シュールレアリスムやダダイズム、もの派などの現代アート的な観点を取り入れたユニークなメソッドを構築した。舞踏家・大野一雄の出世作「ラ・アルヘンチーナ頌」を演出したことでも知られる。
三島由紀夫、澁澤龍彦、瀧口修造、加藤郁乎、埴谷雄高など名だたる作家から讃辞を受けた後、弟子たちによる海外公演で欧州における評価を確立。土方のスタイルは半ば逆輸入のような形で国内の舞台芸術界を席巻した。
四半世紀にわたって作舞をつづけたが、銀座の「セゾン劇場」こけら落とし公演「風神雷神」を上演することなく、1987年肝臓癌により死去。

土方が東福寺付近に住んでいた当時のアパートの入口。1階は製麺所だった。写っているのは男性は大家さん(潘世美氏提供)

1975年に建て替えられたアパート。屋号は当時と同じ「赤門荘」。
企画背景
本企画を立ち上げた理由として、三つの背景がある。
1.開港以前の歴史の再評価
横浜市のアイデンティティは、いうまでもなく「港町」だということである。
この点に関して論は待たないだろう。しかし「諸外国への窓口であった」というプライドを大切にするあまり、横浜には開港以前の歴史を軽視する風潮がある。
横浜は日本有数の大都市であるにも関わらず、城郭を持たない希有な街である。人口150万以上の都市で城下町としての歴史を持たないのは札幌、横浜、神戸くらいであろう。
江戸期の横浜は旗本領であり、大名の統治下にはなかった。それ以前の歴史を鑑みても、大きな歴史事件には関わっていない。その反動からか、あるいは明治維新の成果を誇るショーケース的な役割を担っていたせいか、石器時代の遺跡や東海道の宿場などのわずかな例外を除くと、 まるで開港以前の歴史はなかったかのような扱いを受けている。
しかし開港以前の横浜にも、豊かな歴史は存在した。
たとえば本企画のメイン会場である光明山東福寺である。
東福寺は寛元年間(1243〜1247年)に創建されたとされるが、住職の証言によると、最盛期には現在の桜木町駅付近まで、よその土地を踏まずに歩いて行けたという。江戸時代には22の末寺を有していた、という記録もある。
朱塗りの山門が示すとおり、この寺は江戸幕府から資金援助を受け、復興した歴史を持つ。
東福寺を会場とすることで、開港以前の横浜に光を当てることが、本イベントの目的の一つである。
2.地元所縁の文化人の顕彰
横浜港は海外文化の窓口であった。海運が華やかだった時代、ハマっ子は港の向こうに欧米文化の姿を見ていた。
その弊害なのだろう。横浜には、なんでもよそから持ってくる傾向と地元所縁の文化人を軽視する風潮が、いまだに残っている。
典型的な例は開港150周年記念イベント「Y150」での、フランスから招聘した蜘蛛のロボットである。あのイベントが横浜の他力本願指向を如実に反映していたと考えるのは、的外れではないと思われる。
本企画書執筆者が「横浜市が地元所縁の文化人を軽視している」と考える根拠として、文化人を顕彰する記念館や資料館が極端に少ない事実をあげたい。
横浜は大阪市の270万人を遙かに凌ぐ360万人の人口を誇る。当然、地元所縁の文化人は枚挙にいとまがない。しかし、たとえば国民的歌手と謳われた美空ひばりの資料館やアーカイヴさえない。
「港の見える丘公園」に大佛次郎記念館があるが、そもそもあの建物は大佛の記念館として計画されたものではなく、まず建物ありきの計画で、中身がない建物の使用目的として後づけて記念館にした、という経緯を持つ。この点に関して、裏付けとなる逸話を横浜市役所の企画調整局長だった故・田村明氏(「横浜市の六大事業」を提案者。本企画発案者・檀原の大学時代の恩師)が証言している。
横浜ゆかりの文化人は大勢いるが、彼らを顕彰した制度や施設、イベントはほとんど例がない。
本イベントは、横浜市のこの風潮に対する警鐘としての意味を持つ。
3.「創造都市構想」の補完作業
地方自治体の文化政策には、大別して以下の二通りの方向性があると考えられる。
・地元住民への福利厚生あるいは行政サービスの一環。住民への資本還元。
・外部へのイメージ戦略。地域ブランディングの一手段。
本企画は後者の要素が強いが、これに留まらない。
横浜市は十数年前から「創造都市構想(クリエイティブシティ・ヨコハマ)」を掲げている。2010年以降、横浜市文化観光局は「すべての横浜市民は”アーティスト”である」という都市像をテーマとしているという。そうであるならば、歴史上存在した地元所縁の文化人ならびにアーチストの存在は「都市の共有財産」として、より一層大事にされるべきであろう。
本企画はこの観点から、「創造都市構想」を補完する民間発のプロジェクト、という性格を持つ。
地元所縁の文化人の顕彰は、しばしば歴史の発掘作業を伴う。土方巽と赤門町の関わりは埋もれた歴史だが、これを発掘することで、逆にシチズン・プライドの醸成に寄与することが出来るものと信じる。
●対象となる地域の状況や課題、魅力
東福寺は全盛時代は現在の桜木町のあたりまで社領を有する大きな寺院であったという。1607年までは現在の黄金町駅のあたりに社殿があったそうだが、千葉からやって来た海賊に放火され、現在地に移転したという歴史を持つ。開港前からつづく横浜の歴史の生き証人である。
この寺院が立地する赤英町は高齢者が多く住まう場所で、活気が薄い。注目されることも少ない。しかし背後に野毛の丘陵地を背負い、歴史ある東福寺を抱えるという立地に加え、妙に味のある住宅地が広がっている。歴史を調べると、「昭和の終わりまで温泉旅館が経営されていた」「明治期の大富豪・上郎(こうろう)清助の屋敷の跡地がある」など、歴史的にも興味深い。文化的にも、小説家・吉川英治と舞踏家・土方巽ゆかりの地であり、また大衆作家・長谷川伸(日ノ出町)や小説家・柳美里(黄金町)もこの近隣に所縁を持っている。
本企画は、「開港以前の歴史の再評価」「地元所縁の文化人の顕彰」「『創造都市構想』の補完作業」という三つの意図を持っているが、これは対象となる地域の特徴から導き出された部分が大きい。
●実施活動における文化芸術が果たす役割
このプロジェクトは地元所縁の文化人を顕彰し、その影響下にある現役のダンサーや舞台人の表現を通じて東福寺で奉納舞/奉納芸を行うことが大きな柱である。
またトークイベントを通じて、キャバレーダンサーだったという赤門町時代の土方巽の活動と、後の土方の芸術を接続する試みも行いたいと考えている。
土方が赤門町にいた1960年代は、横浜を舞台にした映画がさかんに作られた時代だった。横浜が光り輝いていた黄金期であり、キャバレーやナイトクラブを軸に港の活気や昭和エレジーを追想することにも繋がる。横浜のレトロな魅力を、ソフトパワーの面から打ち出す企画である。
4.「排除アート」への再考を促す
「アートをつかったまちづくり」が盛んになるにつれ、「好ましくない記号」の排除、雑草のような異趣の消滅、行きすぎた管理体制による無難極まりない風景の展開が問題視されている。
アートを利用した街の浄化に対し、美醜反転、いかがわしさ、芸能性、ある種の穢れ、聖性などありとあらゆる矛盾を内包したものとして舞踏や身体芸術を投げかける。
「これは純粋なアートで綺麗なものである」
「これはいかがわしいもので、出来ればない方が良い」
などというものの見方に対し、この地に暮らした土方巽をアイコンにして一石を投じる。